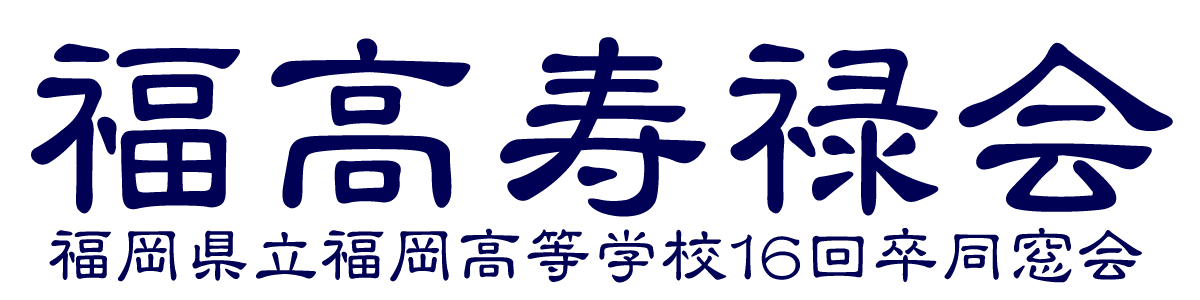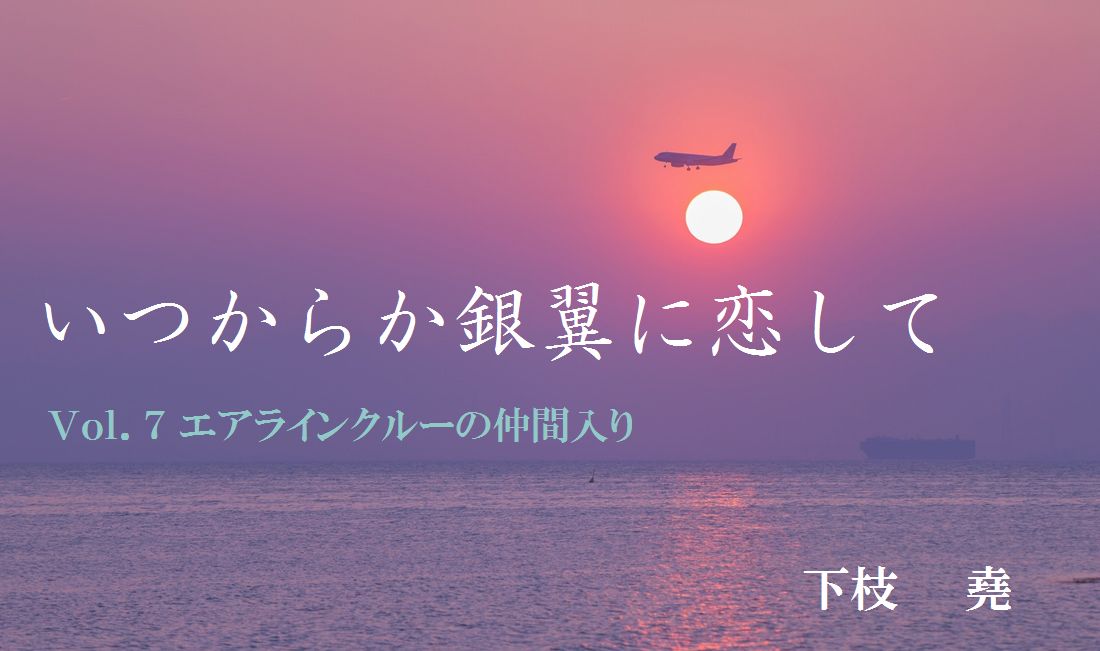いつからか銀翼に恋して Vol.7 エアラインクルーの仲間入り
2018/05/06
夢のジェット機――ボーイング727
1969年10月14日、ビーチクラフト機での大型旅客機対応飛行訓練、地上訓練をすべて完了し仙台乗員基礎訓練所を卒業、東京に移動し大型実用機の訓練に進みました。
我がクラスに与えられた機種はボーイング727型機、日本の国内線ジェット機として航空三社(日本航空、全日空、日本国内航空)で統一導入した3つのエンジンを後部に配する短距離路線用の高性能機種で、橋幸夫、吉永小百合のデュエットで歌謡曲「そこは青い空だった」でも歌われていた傑作機でした。
私たちは3人目のパイロット(Second Officer)として航空機関士の資格を取る訓練に入り、座学、整備工場での整備実習、シミュレーター訓練、アメリカワシントン州モーゼスレーク(現在はMRJの試験飛行基地でもある)での実機訓練を受けたのち国内線で教官同乗の路線訓練に入りました。
訓練中に聞いた「よど号」ハイジャック事件
訓練生として国内路線を飛行中の1970年3月31日、羽田発福岡行きの愛称「よど号」(B727)が日本赤軍にハイジャックされる事件が起きました。
これは日本で初めてのハイジャックで、福岡空港では一部始終がテレビ放映され皆さんもご覧になったことでしょう。犯人と交渉ののち、乗客の身代わりとして運輸次官の山村新次郎代議士を乗せ北朝鮮の平壌に向け飛び立ちました。
ちなみに、この便のE副操縦士は筑紫丘高校の出身で、親しくさせていただいた先輩機長のお一人です。途中、韓国金浦空港に誘導されるなどミステリアスな経過をたどりましたが、何とか平壌の飛行場に着陸。赤軍派の犯人たちは北朝鮮に保護され48年後の今も解決していません。
平均年齢20歳代の若いクルー
約半年の路線訓練、シミュレーター訓練を経て、運輸省航空局の国家試験に合格し「航空機関士技能証明」を取得、8月4日、晴れてエアラインクルーの仲間入りをしました。
当時、B727は新しい機長の養成機種で、20歳後半から30歳代の若い機長が大半で、3人のパイロットの平均年齢が20歳代というのが大半でした。その上、スチュワーデスも20歳そこそこの若い人ばかりの時もあり、明るい生き生きとした職場でした。
国内線は羽田から千歳往復、福岡または大阪往復など日帰り4区間乗務、3区間飛んだあと宿泊し連続勤務するパターンなどで月間60飛行時間程でした。沖縄の那覇にも飛んでいましたが当時は国際線でパスポート所持、ドル持参でした。
航空機関士の仕事は、出発前の外部点検、機体作動確認、そして運航中はエンジン、電気系統、燃料、油圧、機内の空調及び与圧の調整管理を担当。離着陸の諸データ算出や、推力調整等運航全般にわたります。この経験で航空機のシステム全般に精通することができ、その後のパイロット人生に貴重な経験を得ることとなりました。
※今の旅客機はコンピュータなど機材装置の進化により、機長・副操縦士二人で運航が可能となり、航空機関士は職を失いました。
犠牲者ご家族を千歳に運んだ思い出
B727グループに所属中の1970年7月2日、東亜国内航空のYS-11が函館で横津岳に激突し68名の犠牲者が出たときは、当日の深夜、犠牲者ご家族を海霧に覆われた千歳までお運びしました。また、同30日には全日空機と航空自衛隊のF86戦闘機が岩手県雫石上空で空中衝突し162名が犠牲になる事故が起こりました。
日本の空はまだまだ不安全要素が多く、これを機に航空路と訓練空域の分離、航空管制レーダーの配備が促進されることになります。