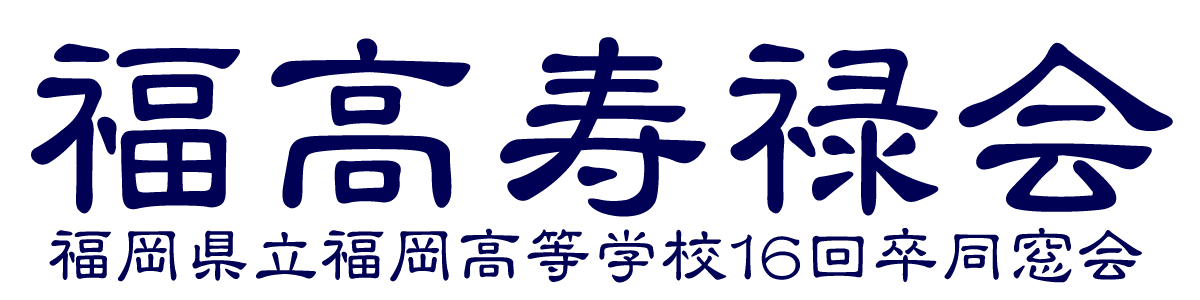町家からの眺め
2016/06/21
博多町家ふるさと館 館長/長谷川 法世
これからは仕事場と住まいは別になる、と先生は言った。
 冷泉小学校で、あれは何の授業だったか、文化的な住まいについて教わったことがある。職住同一と職住分離の住まいのことだった。
冷泉小学校で、あれは何の授業だったか、文化的な住まいについて教わったことがある。職住同一と職住分離の住まいのことだった。
「仕事場や店と同じ建物に住んでいる人、手を上げて」
と先生が質問した。大半の生徒が手を上げた。博多は商人の町だもの、職住同一だ。中洲だって一つ屋根の下に店と住まいがあった。
「これからは、仕事場と住まいは別になる。それが文化的ということだ」
先生が高らかに言った。
「えーっ」
全員があっけにとられて、大きな声を上げた。生徒の一人が聞いた。
「そんなら、どこに家はあるとですか」
「離れたところにあるとたい。毎日店に通うとたい、電車で」
「電車でーっ?」
町家暮らしはタクシーにも乗れない
先生はアメリカを手本にした郊外型住宅地、つまりベッドタウンの話をしていたのだろう。けれど、博多の小学生には電車で店に通うなんて不便なことが、なぜ文化的なのか分からなかった。店と寝るとこがいっしょなら、時間も電車賃も節約できる。第一、西鉄の市内電車や急行電車はよそ行きで乗るものだ。正月の三社参りで、宮地岳神社や大宰府に行くときの特別な乗り物だ。それを毎日乗るなんて贅沢な。
福高に入るとサラリーマン家庭の生徒が大半で、香椎や多々良から電車で通ってきている。博多の人間にはそれでようやく職住分離の住まい方が実際に分かったのだった。
博多総鎮守・櫛田神社のそばに住んで、もちろん商売をしている人が、冗談で言う。
「一生のうちにいっぺんで良かけん、言うてみたかとですよ。中洲で飲みよって終バスに乗り遅れてしもうた、て。タクシーで帰って、2000円もかかってしもうた、て。俺やら、タクシー停めたら運転手さんに怒られますもん。そげん近かとなら這うて帰んない、て」
通り庭は肥桶が通れる幅
 そういう暮らし方の原点が、博多の町家なんだ。町家には玄関というものがない。単なる入り口。入れば店だ。それが普通だから、街に生け垣や塀や見越しの松なんてものはない。門もない。1階には廊下もない。あるのは通り庭という土間だ。中庭まで続いている。中庭の先は、ウナギの寝床とよばれる長い敷地の奥の蔵や別棟だ。
そういう暮らし方の原点が、博多の町家なんだ。町家には玄関というものがない。単なる入り口。入れば店だ。それが普通だから、街に生け垣や塀や見越しの松なんてものはない。門もない。1階には廊下もない。あるのは通り庭という土間だ。中庭まで続いている。中庭の先は、ウナギの寝床とよばれる長い敷地の奥の蔵や別棟だ。
通り庭の一番の用途は、し尿の汲み出しだ。一戸にひとつ、落とし便所が付いている。それが、長屋との決定的な差だ。隣家と壁がべったりくっついているけれど、ちゃんとした独立家屋だ。だから便所があり、通り庭がある。それでなければ、山笠だのなんだの町内ごとでひとこと言えない。江戸時代、土地持ち家持ちが町人と呼ばれた。
博多町家は平均の間口が2間~4間と言われる。町は全国的に間口税だったので、できる限り間口を狭くしている。間口2間の家でも、通り庭が付いている。肥桶がやっと通りぬけられる幅だ。それでもだから一人前の町人なんだ。
博多町家ふるさと館の館長になって14年目になる。福高同窓生の中でも少々変わった立ち位置から、思い出や現在やこれから(そんな余裕はないが)を語ってみまっしょう。