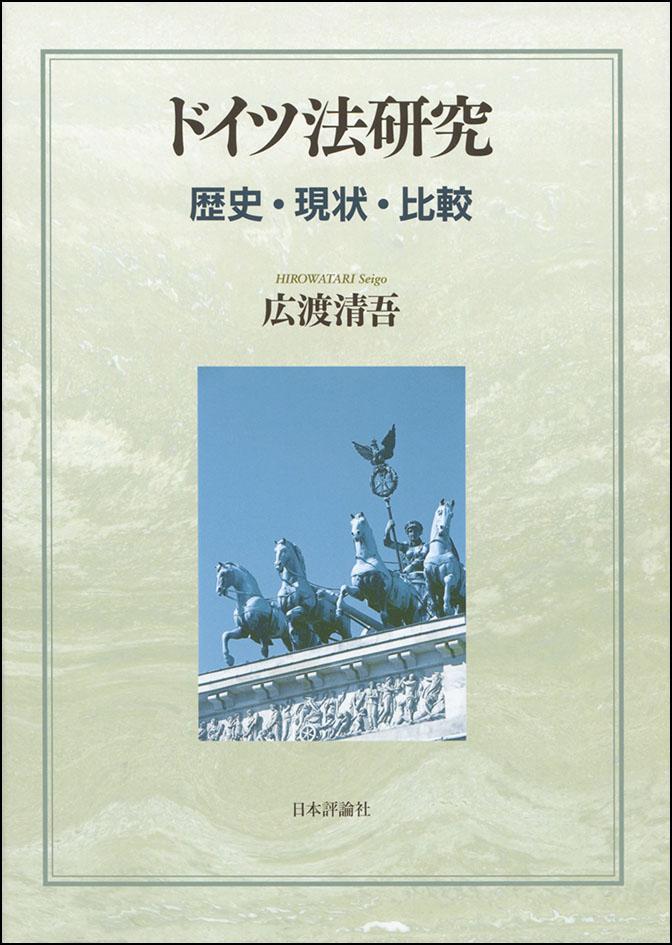「ドイツ事初め」の頃
廣渡 清吾
研究生活の集大成として
大学を卒業して法学部の民法の助手になったころ、研究室で、毎日、毎日、ドイツの民法教科書を読んでいました。読むといっても、でてくる単語は片っ端から辞書を引かないと意味が分からない、学生時代は第2外国語でドイツ語を取りましたが、文法が分かっている程度ですから法律書を前にすると初心者同様で、ノートに全訳する、つまり一字一句、ドイツ語を日本語に移し替えるというのが仕事でした。それも、1日がかりで3頁できれば、「今日は進んだ!」という調子でした。 この当時のノート数冊、いまも手許にあります。どうなることかと思いながらのドイツ事初めでしたが、それでも夏休みをすぎると、教科書を終わって、専門の論文を読めるようになりました。
3つの河の街――パッサウで
読めるようになっても、話すのはまた、別のレベルの問題ですね。ぼくの第1回目のドイツ行きは33歳のときですから、年齢的に遅かったです。農村調査グループのメンバーとしてドイツのあちこちを歩きました。さすがにいきなり調査は無理なので、その前に語学学校で2カ月間、はじめてちゃんとドイツ語を学びました。場所は、オーストリア国境に近いパッサウという町です。とても綺麗な町で、ぼくには「おとぎの国」のようにロマンティックに映りました。
ここは「3つの川の町」とよばれる観光地でもあり、うち1つがドナウ川です。この町のレストラン「金色の十字架」には、「ドナウ・フィッシュ」というタイトルのメニューがありました。「ドナウ魚」という名前の魚がいるのかと尋ねましたら、「ドナウ川で取った魚」のことで「その日に取れたのを出すのさ」でした。ぼくの場合は、小ぶりの鯉(のようなもの)の唐揚げにレモンをかけて食べました。
フランスに近いシュタウフェンという小さな町のレストランでも似たようなことがありました。蛙(ドイツ語でフロッシュ)のメニューがあったので、御世辞のつもりで、「この蛙はパリからの輸入ですか」と聞いたら、「駅前に池があるだろう、あそこで取ったものだよ」でした。鶏のささみのように淡泊で、リンゴジャムをつけて食べました。ついでながら珍しい肉料理としては、アフリカ直輸入のライオンのステーキがあります。ヒトラーの山荘があった南ドイツのベルヒテスガーデンのレストランにメニューがあるようですが(ホントかな?)、残念ながらまだ食べていません。
ホテルラウンジで“意地悪”される!?
初心者の失敗は、ドイツに着いたばかりのミュンヘンのホテルのラウンジで、「コーヒー」を注文したときです。「ありません」という返事、でも周りではみなさん確かに「コーヒー」を飲んでいます。それを問いただす技量もなく、やむをえず、オレンジジュースにしましたが、「ひょっとして意地悪されている?」とひがみました。

場数を踏んで分かりましたが、格式の高い(と必ずしも限りませんが)カフェでは、コーヒーや紅茶はカップではなく、小ぶりのポットでしかださないのでした(カップ2杯分の量で値段は1.7倍くらい。もちろん飲むためのカップがついてきます)。つまり、注文するときに、ぼくは教わった通りに、「アイネ タッセ カフェー ビッテ」(A cup of coffee please)といったのですが、「アイン ケンヘエン カフェー ビッテ」(A pot of coffee please)というべきだったのでした。
”飯の種”ドイツから勲章をいただく
本格的な留学は、農村調査の1年後でした。ドイツのアレクサンダー・フォン・フンボルト財団という学術助成機関から2年間の奨学金をもらって、中部ドイツのギーセンという人口約6万人の町にある大学で、「ナチス時代の法と法学」を研究しました。この研究の成果がどうなったかは、最初に御案内した近著に詳しいです(また宣伝していますね)。
日本からの研究者が珍しかったからでしょうか、地元の新聞がインタヴューしてくれて、「夕食は自炊で日本食!」という、やや心外な、写真入りの大きな記事になりました。家族は半年後に合流しましたが、自炊のおかげで、1週間は違った献立をならべる自信?がつきました。
こののちにもいろいろあって、通算5年近くドイツで生活することになりました。定年退職前の今年の2月に思わぬことでしたが、ドイツから勲章をいただきました。日独学術交流の発展に貢献したという理由ですが、ドイツは「飯の種」であり、こちらからお礼をしなければならないところですから、いたく恐縮しました。これから多少なりとも恩返しをと思っています。